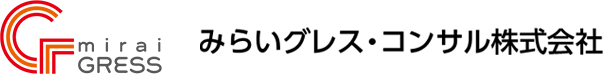💡【ISO審査対応】マネジメントシステム審査における「観察事項(オブザーベーション)」とは?対応判断の基準を徹底解説
ISMS、QMS、EMSなどのISOマネジメントシステム(MS)認証審査では、
「観察事項(オブザーベーション)」という指摘が入ることがあります。
これは不適合(指摘事項)とは異なり、対応義務がないため、
組織として対応すべきか迷うポイントです。
🧐 観察事項とは?不適合との違い
不適合とは、規格要求事項や社内ルールに違反している状態を指します。
是正処置が必須であり、期日内の対応報告が求められます。
軽微なもの(マイナー)と重大なもの(メジャー)に分類されることもあります。
一方、観察事項は、現時点では規格に適合しているものの、
将来的に不適合につながる可能性がある事象です。
対応するかどうかは組織の自由です。
是正処置の義務はありません。
観察事項は、審査員が組織のマネジメントシステムをより良くするために提供する
貴重なインプットであると言えます。
⚖️ 観察事項への対応におけるジレンマ
観察事項への対応を巡っては、組織が以下のようなジレンマに直面します。
慎重な判断
観察事項の中には、組織によっては対応が不要なものも存在する可能性があります。
これらを含めてすべての観察事項に対応しようとすると、業務負荷が増加し、マネジメントシステムの運用が形骸化するリスクを招く恐れがあります。
また、対応によって他の業務に支障が生じる可能性もあるため、対応の要否については慎重な判断が求められます。
対応しない選択肢の是非
観察事項は対応しないことも正式に認められています。
ただし、対応しない理由を明確に記録しておくことが重要です。
これにより、次回審査で「検討していない」と指摘されるリスクを回避できます。
🎯 観察事項に対応すべきか?判断基準は「ISO認証をやめても必要か」
観察事項への対応を判断する際の有効な視点は、
「ISO認証をやめた後も、その対応策を継続する価値があるか?」という問いです。
対応すべき観察事項の例
- 顧客満足度の向上、コスト削減、リスク低減など、事業成果に貢献する内容
- 法令遵守や重大なリスク回避につながる内容
対応しなくてもよい観察事項の例
- 実務に影響がない形式的な文書修正
- 対応にかかる工数やコストに対して改善効果が乏しいもの
- 対応によって業務フローが混乱する可能性があるもの
📝 観察事項対応の判断プロセスと記録の重要性
観察事項は「改善の機会」であり、「対応の義務」ではありません。
ISOマネジメントシステムは、審査員のためではなく、組織のために存在するものです。
対応の判断は、以下のステップで行うことをおすすめします。
- 組織の事業への貢献度、リスク低減、業務負荷を総合的に評価する
- ISO認証がなくても継続すべきかを自問する
- 対応する・しないに関わらず、判断理由を記録に残す
❓ よくある質問(Q&A)
Q1. 観察事項は必ず対応しなければならないのですか?
A. いいえ、観察事項は不適合ではないため、対応の義務はありません。ただし、対応することで将来的な不適合を防ぐことができる場合もあります。
Q2. 対応しない場合、審査で問題になりますか?
A. 対応しないこと自体は問題ではありませんが、「なぜ対応しないのか」を検討し、記録しておくことが重要です。これにより、次回審査での指摘を回避できます。
Q3. 観察事項が多いと審査評価に影響しますか?
A. 直接的な評価には影響しませんが、観察事項が多い場合は、マネジメントシステムの改善余地が多いと見なされる可能性があります。
Q4. 観察事項を放置するとどうなりますか?
A. 放置しても即座に問題になることはありませんが、将来的に不適合につながる可能性があるため、対応の必要性を検討すべきです。
弊社研修・コンサルティングのお問合せ: こちら