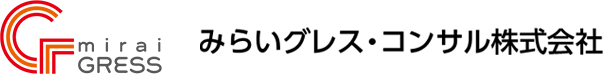📝【ISO認証取得企業向け】マネジメントシステムが「定着しない」二大原因とその解決策|ISMS・QMS・EMS対応
ISO認証(ISMS、QMS、EMSなど)の第三者認証を取得したにもかかわらず、「マネジメントシステムが組織に定着しない」「ISO活動が形骸化している」と悩む企業は少なくありません。
せっかく時間と費用をかけて構築・運用しているのに、「審査のための活動」になってしまい、現場社員が関わりたがらない状態では、ISOマネジメントシステム本来の価値を発揮できません。
組織によって事情は異なりますが、マネジメントシステムが定着しない原因には、共通する重要なポイントが2つあります。
🧐 原因1:ISO規格特有の「難解な文書と専門用語」
ISOマネジメントシステム文書(マニュアル、規程、手順書など)が現場に定着しない最大の理由の一つは、内容が難しく、現場の言葉で書かれていないことです。
📌 ISO用語が日常業務の理解を妨げる
ISO規格には、「トップマネジメント」「マネジメントレビュー」「文書化された情報」など、日常業務では使用しない専門用語が頻出します。
これが、現場社員が「ISOは難しい」「自分たちの仕事とは関係ない」と感じる大きな原因です。
✅ 具体例と対策
- 例:トップマネジメント
- 規格上の意味: 「最高位で組織を指揮し、管理する個人またはグループ」
- 現場での理解: 多くの企業では「社長」「経営層」「役員会」など
- 💡 解決策: マニュアルや規程には、実際に使用している名称(例:「社長」「役員会」)を記載することで、理解が深まります。
「マネジメントレビュー」は「経営層によるシステム見直し会議」、「文書化された情報」は「規程・手順書・記録」など、現場の言葉に置き換えることで、ISO文書の読みやすさと実用性が向上します。
⚙️ 原因2:「審査対策向け」の無理なルール設定と業務乖離
マネジメントシステムが定着しないもう一つの原因は、組織の実態に合わない過剰なルールや、形式的な審査対策に特化した仕組みの導入です。
📉 実業務との乖離が形骸化を招く
他社の事例をそのまま導入した結果、日常業務と乖離したルールが生まれることがあります。
- 現場の認識:「このルールはISO審査のためだけ」「実際の業務とは違う」
- 結果: 規程は読まれず、ISO活動は「毎年のイベント」「とりあえず実施」と見なされ、形骸化が進行
- 本来の目的: ISOマネジメントシステムは、組織の目標達成と継続的改善のための「経営ツール」であるべき
💡 解決策:システムのスリム化と業務統合
- 不要な文書・記録の削減: ISO規格が必須としていない文書や記録は見直し、スリム化を図る
- 現場主導の見直し: 担当者が「このルールは必要か?」「もっと効率的な方法は?」と問い、業務フローに即した規程へ修正
- ISO活動=日常業務: 「審査対策」ではなく、「より良い仕事をするための仕組み」として、組織全体に意識を浸透させる
🚀 ISOマネジメントシステムを定着させるための改善アクションプラン
上記2つの原因を改善しない限り、ISO事務局以外の社員は「できればISO関連に関わりたくない」と感じ、規程を読まず、活動に参加しなくなります。
✅ 定着のための2つの改善ポイント
- 用語の置き換えと文書の平易化: 難解なISO用語を現場の言葉に置き換え、誰でも理解できる文書に改訂する
- 実態に即したルールへの見直し: 実業務と一致しない、または過剰なルールを排除し、「審査対策」ではなく、組織に最適な仕組みに修正する
これにより、社員はISOを「面倒な作業」ではなく、「日々の業務改善ツール」として認識し、マネジメントシステムは組織の力として定着していきます。
❓よくある質問(FAQ)
Q1. ISOの文書が難しくて現場が読まないのですが、どうすればいいですか?
A. 規格用語を現場の言葉に置き換え、誰でも理解できるように文書を平易化することが有効です。
Q2. ISO活動が「審査のため」だけになってしまっています。改善方法は?
A. 実業務に合ったルールへ見直し、不要な文書・記録を削減することで、業務改善ツールとして再認識されます。
Q3. ISO認証を取得したが、社員の参加意欲が低いです。どうすれば?
A. ISO活動が「より良い仕事のための仕組み」であることを、トップから現場まで浸透させることが鍵です。
弊社コンサルティングのお問合せ: こちら