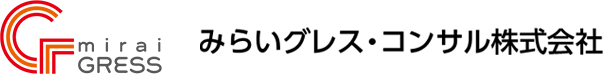内部監査の本質とは?問題発見ではなく「組織改善の最後の砦」
内部監査に対する誤解とその背景
多くの組織員は、「監査=問題点探し」と捉えがちです。
「指摘されたら困る」、「無難に乗り切りたい」といった心理から、
都合の悪い情報を控える傾向も見られます。
しかし、内部監査は組織の健全性を守る“最後の砦”であり、
問題発見ではなく改善の機会を提供する業務なのです。
内部監査は“火種”を見つける防火壁
日常業務に慣れると、非効率な業務やリスクに気づきにくくなります。
これは怠慢ではなく、客観的な視点の欠如によるものです。
第三者である監査員が業務を確認することで、
初めて潜在的なリスクが明らかになります。
もし監査で問題が見つからなければ、次に発覚するのは顧客クレームや事故、
外部指摘など、より深刻な事態です。
だからこそ、内部監査は、問題が大きくなる前に火種を発見する「防火壁」として機能します。
指摘事項は「問題」ではなく「改善チャンス」
監査の現場では、指摘事項を「問題」と捉えるのではなく、
「改善のチャンス」と考えることが重要です。
監査員は現場担当者の努力に敬意を払い、
客観的な視点と現場の意見を融合した建設的な対話を行います。
これは単なる「指摘と回答」ではなく、組織の成長を促す意見交換の場なのです。
まとめ:監査を“成長の機会”に変える方法
監査は罰則の場ではなく、組織の回復力と業務品質を高めるチャンスです。
「監査=最後の砦」、「指摘=改善の機会」と捉え直すことで、
組織は一段階上の成長を遂げることができます。