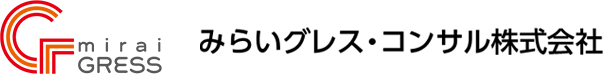社員のための規程づくり
多くの企業が、ISMS・QMS・EMSなどの第三者認証の取得を通じて、業務品質や組織の信頼性を高めようと努力されています。これは間違いなく企業成長にとって重要な一歩です。
ですが、「せっかく認証を取得したのに、社員が規程を読まない」「規程が現場で機能していない」といった声が少なくありません。
それはなぜか。
結論から言えば、規程が“社員の言葉”になっていないからです。
規格用語の“そのまま転写”がもたらす距離感
第三者認証の規格要求事項をほぼそのまま写したような社内規程をよく見かけます。
もちろん、基準に準拠することは重要ですが、それだけでは“使える規程”にはなりません。専門用語が並ぶ規程は、実務に直接関わらない社員にとっては読みづらく、活用されずに終わることがほとんどです。
せっかく策定したはずの規程が、机上の空論となってしまっては本末転倒です。
業務に根ざした言葉で語られる規程へ
重要なのは、社員一人ひとりが「これは自分の業務に必要なものだ」と感じ、実践できるような内容に仕上げることです。
そのためには、抽象的な規格要求事項を、自社特有の業務や状況に置き換え、日常業務に落とし込んだ表現で記述し直す必要があります。
“合わせる”ではなく“強化する”という視点
認証取得のために無理やり業務を変える——その結果、現場が混乱するケースも珍しくありません。
ですが、既に自社にとって有効な業務プロセスがあるなら、それを活かしてこそ本当の意味でのマネジメントシステムになります。
業務に規格を合わせるのではなく、業務を規格で強化する。
この考え方こそが、実務に根差した“生きた規程”を育てる第一歩です。
規程は「手続き」ではなく「共通言語」である
社内規程は、単なる認証の条件ではありません。
それは、社員が迷わず業務を進めるための「羅針盤」であり、業務品質の維持やリスク管理、そして顧客への価値提供を支える「共通言語」です。
その作成・修正にあたっては、ぜひ次の3つの問いを自社に向けてみてください。
- この規程は【誰が・いつ・どういう場面】で使うものか?
- この規程によって、社員は【何を理解し・どう行動】すればいいのか?
- この規程の存在意義は【どんな課題を解決し・どんな価値】につながるのか?
これらに真剣に向き合えば、認証の“ため”ではなく、社員の“ため”の社内規程づくりへと自然に転換できるはずです。